問題はこちら。院試対策・物理学の勉強にご利用ください。
また、誤植があればお問い合わせください。
問1:1次元井戸型ポテンシャル
1-1.
2つの異なる波動関数\(\psi_1(x) \neq \phi_2(x)\)に対して、シュレーディンガー方程式
$$- \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi_1(x) + V(x)\phi_1(x) = E\phi_1(x) …(1)$$
$$- \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi_2(x) + V(x)\phi_2(x) = E\phi_2(x) …(2)$$
が成り立つと仮定する。\((1)\times\phi_2(x) – (2)\times\phi_1(x)\)より
$$\psi_2\frac{d^2}{dx^2}\phi_1 – \phi_1\frac{d^2}{dx^2}\phi_2 = 0$$
$$\frac{d}{dx}\left(\phi_2\frac{d}{dx^2}\phi_1 – \phi_1\frac{d}{dx^2}\phi_2\right) = 0$$
$$\psi_2\frac{d}{dx^2}\phi_1 – \phi_1\frac{d}{dx^2}\phi_2 = C (Cは任意定数)$$
\(x \rightarrow \pm \infty\)で\(\phi_1 = \phi_2 = 0\)となることを課すと、\(C = 0\)。よって
$$\frac{1}{\phi_1}\frac{d}{dx}\phi_1 = \frac{1}{\phi_2}\frac{d}{dx}\phi_2$$
両辺を\(x\)について積分して
$$log\phi_1 = log\phi_2 + C_1$$
$$\phi_1 = C’\phi_2 (C_1, C’ は任意定数)$$
この結果は、仮定と矛盾する。したがって、縮退は生じない。
1-2.
$$- \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi(x) + V(x)\phi(x) = E\phi(x) …(3)$$
と、(3)において\(x \rightarrow – x\)とした(\(V(-x) = V(x)\)であることを利用)
$$- \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi(-x) + V(x)\phi(-x) = E\phi(-x) …(4)$$
に対して、
$$\phi(x) = C\phi(-x) (Cは任意定数)$$
が成り立つ。また
$$\phi(-x) = C\phi(x)$$
も成り立つので
$$\phi(x) = C^2\phi(x) \rightarrow C = \pm 1 $$
以上より、
$$
\phi(x) = \begin{cases}
\phi(-x) & (偶関数)\\
– \phi(-x) & (奇関数)
\end{cases}
$$
1-3.
\(|x| > a\)でのシュレーディンガー方程式は
$$- \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi(x) = E\phi(x)$$
これを解くと一般解は
$$\phi(x) = Asin\alpha x + Bcos\alpha x$$
となるが、\(\phi(x)\)は偶関数の場合を考えるので
$$\phi(x) = Acos\alpha x$$
\(|x| < \alpha\)でのシュレーディンガー方程式は
\begin{align*}
&- \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi(x) + V_0\phi(x) = E\phi(x)\\
&\frac{d^2}{dx^2}\phi(x) -\frac{2m}{\hbar ^2}(V_0 – E)\phi(x) = 0
\end{align*}
これを\(x \rightarrow \pm \infty\)の境界条件の下で解くと
\(x \rightarrow \pm \infty\)では波動関数\(\phi(x)\)は発散しないため
\[
\phi(x) =
\begin{cases}
Ce^{\beta x} & (x < -a)\\
Ce^{-\beta x} & (x > a)
\end{cases}
\]
となる。以上のA, Cは任意定数である。
また、\(x = a\)での境界条件として、\(\phi(x), \ \frac{d\phi(x)}{dx}\)が連続であることを用いると
\begin{align*}
&Acos\alpha a = Ce^{-\beta a} \ …[1]\\
&-\alpha Asin\alpha a = -\beta Ce^{-\beta a} \ …[2]
\end{align*}
が得られる。\([2]/[1]\)を計算すると
$$\alpha tan\alpha a = \beta \ …[3]$$
が得られる。
1-4.
[3]の両辺に\(a\)をかければ
$$\eta = \xi tan\xi \ …[4]$$
が得られる。また、
$$\eta ^2 + \xi ^2 = a^2(\alpha ^2 + \beta ^2) = \frac{2mV_0}{\hbar ^2}a^2 \ …[5]$$
の関係がある。よって、[4], [5]をグラフに表すと以下のようになる。
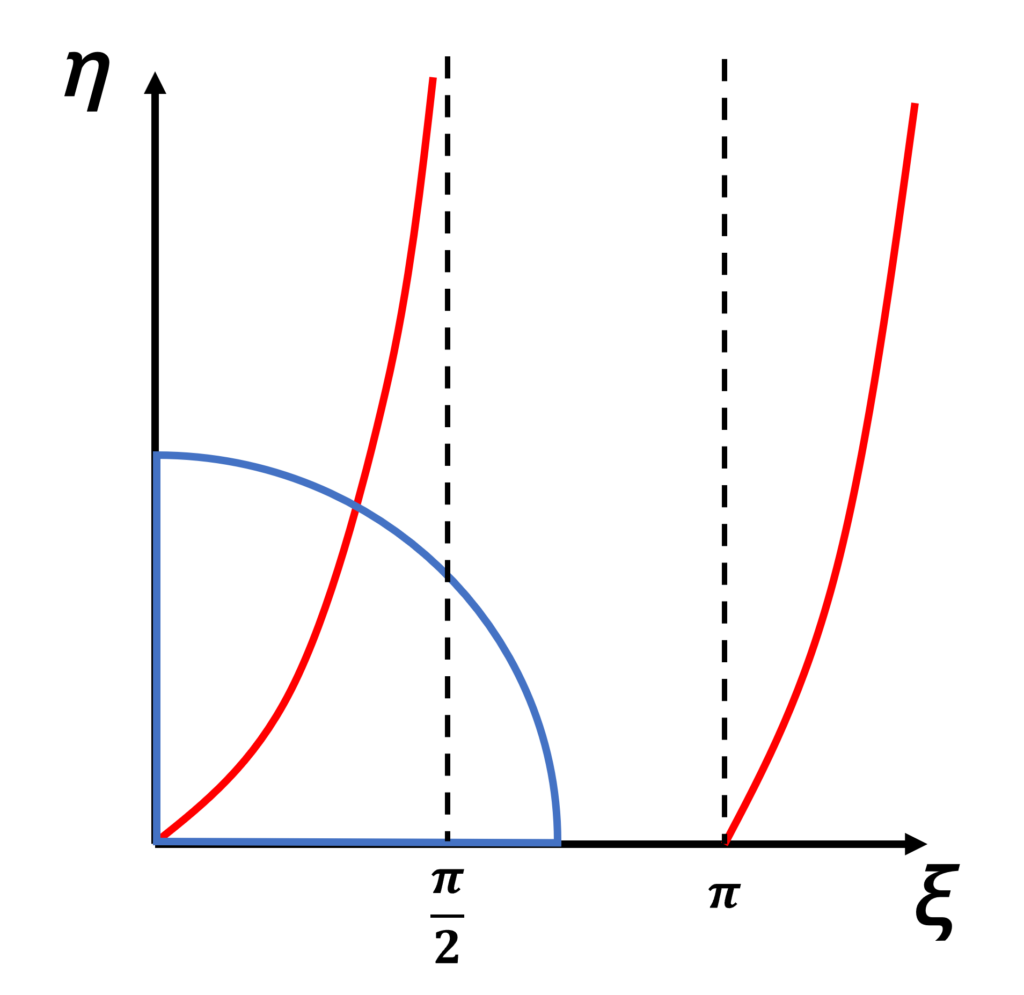
ここで、赤い曲線は[4]を示している。また、青い曲線は[5]の関係式を示しており、半径\(\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar ^2}}a\)の円である。
よって、エネルギー固有状態が唯一つになるための条件は、\(\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar ^2}}a < \pi\)である。
1-5.
\(\frac{V_0 ma^2}{\hbar ^2} << 1\)であるから、[5]より\(\xi << 1\)であることも明らかである。よって、[4]は
$$\eta \neq \xi\cdot\xi = \xi ^2$$
と近似することができる。これを[5]に代入すると、
$$\xi ^4 + \xi ^2 = \frac{2mV_0}{\hbar ^2}a^2$$
という\(\xi\)の4次方程式が得られる。これを解けば、
$$E = \frac{\hbar ^2}{4ma^2}\left(-1 + \sqrt{1 + \frac{8mV_0}{\hbar ^2}a^2}\right)$$
が得られる。ここで、求めた\(E\)に含まれる平方根の部分は
\begin{align*}
\sqrt{1 + \frac{8mV_0}{\hbar ^2}a^2} &\neq (1 + 8\lambda)^{\frac{1}{2}}\\
&= 1 + 4\lambda -8\lambda ^2
\end{align*}
のように展開することができる。 すなわち
$$E \neq \frac{\hbar ^2}{ma^2}(\lambda – 2\lambda)$$
と書くことができる。
問2:電気双極子モーメントの摂動論
2-1.
\begin{align*}
[\mathbf{L}^2, L_z] &= [L_x^2 + L_y^2 + L_z^2, L_z]\\
&=L_x[L_x,L_z]+[L_x,L_z]L_x + L_y[L_y,L_z] + [L_y,L_z]L_y\\
&=L_x(-i\hbar L_y) + (i\hbar L_y)L_x + L_y(i\hbar L_x) + (i\hbar L_x)L_y\\
&= 0
\end{align*}
よって、\(\mathbf{L}^2, \ L_z\)は同時対角化可能である。
また、
$$[H_0, L_z] = \frac{1}{2I}[\mathbf{L}^2, L_z] = 0$$
なので、\(H_0, \ L_z\)は同時対角化可能である。
$$[\mathbf{L}^2, H_0] = \frac{1}{2I}[\mathbf{L}^2, \ \mathbf{L}^2] = 0$$
なので、\(\mathbf{L}^2, \ H_0\)は同時対角化可能である。
2-2.
\begin{align*}
H_1 &= – p\varepsilon cos\theta\\
&= – p\varepsilon\frac{z}{r} \propto z
\end{align*}
ここで、\(L_z = xp_y – y_px\)であり、これに\(z\)が含まれていないことから\(L_z, \ H_1\)は同時対角化可能である。
\(|l, m\rangle\)は\(L_z\)の固有ベクトルである。\(L_z, \ H_1\)は同時対角化可能であることより、\(|l, m\rangle\)は\(H_1\)の固有ベクトルでもある。よって、\(m’ = m\)を満たす必要がある。
2-3.
$$|\phi _n\rangle = \displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}|\phi_m^{(0)}\rangle$$
と展開する。\(C_{nm} = C_{nm}^{(0)} + \lambda C_{nm}^{(1)}+ O(\lambda ^2)\)とする。ここで、シュレーディンガー方程式より
$$H|\phi _n\rangle = E_n|\phi _n\rangle $$
であるから、
\begin{align*}
(H_0 + \lambda H_1)|\phi _n\rangle &= (H_0 + \lambda H_1)\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}|\phi_m^{(0)}\rangle\\
&= \displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}E_{m}^{(0)}|\phi_m^{(0)}\rangle\\
& \ + \lambda\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}H_1|\phi_m^{(0)}\rangle\\
&= \displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}E_n|\phi_m^{(0)}\rangle
\end{align*}
のように式変形ができる。最後の2つの辺に対して、左から\(\langle \phi_k^{0}|\)をかけると
\begin{align*}
&\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}E_m^{(0)}\delta_{km} + \lambda\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}\langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_m^{(0)}\rangle C_{nm}\\
&= \displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}C_{nm}E_n\delta_{km}\\
&C_{nk}(E_k^{(0)} – E_n) + \lambda\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}\langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_m^{(0)}\rangle C_{nm} = 0
\end{align*}
ここで\(C_{nm} = \delta_{nm}\)とすると、上式は\(\lambda\)の2次以上の項を無視して
\begin{align*}
&(\delta_{nk} + \lambda C_{nk}^{(1)}){E_k^{(0)} – E_n^{(0)} – \lambda E_n^{(1)}}\\
& \ + \lambda\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}(\delta_{nm} + \lambda C_{nm}^{(1)})\langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_m^{(0)}\rangle = 0
\end{align*}
\(\lambda\)の次数で整理すると
\begin{align*}
&\delta_{nk}(E_k^{(0)} – E_n^{(0)})\\
& + \lambda {C_{nk}^{(1)}(E_k^{(0)} – E_n^{(0)}) – E_n^{(1)}\delta_{nk} + \langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_m^{(0)}\rangle} + O(\lambda ^2)\\
&= 0
\end{align*}
上式において、\(\lambda\)の1次について等式が成り立つ必要がある。よって
i)\(k = n\)の場合
$$E_n^{(1)} = \langle\psi_n^{(0)}|H_1|\psi_n^{(0)}\rangle $$
ii)\(k \neq k\)の場合
$$C_{nk}^{(1)} = \frac{\langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} – E_k^{(0)}}$$
が成り立つ。したがって
\begin{align*}
|\phi_n\rangle &= \displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}(\delta_{nm} + \lambda C_{nm}^{(1)})\langle\psi_k^{(0)}\\
&= |\phi_n^{(0)}\rangle + \lambda C_{nn}^{(1)}|\phi_n^{(0)}\rangle + \lambda\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty}\lambda C_nm^{(1)}|\phi_m^{(0)}\rangle \\
&= |\phi_n^{(0)}\rangle + \lambda\displaystyle\sum_{m\neq n}^{\infty}\frac{\langle\psi_m^{(0)}|H_1|\psi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} – E_m^{(0)}}|\psi_m^{(0)}\rangle
\end{align*}
上では、\(C_nn^{(1)}\}は任意の値をとるので、0とした。以上より
$$|\phi_n^{(1)}\rangle = \lambda\displaystyle\sum_{m\neq n}^{\infty}\frac{\langle\psi_m^{(0)}|H_1|\psi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} – E_m^{(0)}}|\psi_m^{(0)}\rangle$$
2-4.
$$E_{lm}^{(1)} = \langle l,m|H_1|l, m\rangle$$
ここで、\(l’ \neq l \pm 1\)であるから
$$E_{lm}^{(1)} = 0$$
また、2-3の結果を用いると
\begin{align*}
E_{lm}^{(2)} &= \langle \psi_n^{(0)}|H_1|\psi_n^{(1)}\rangle\\
&= \langle \psi_n^{(0)}|H_1|\left(\displaystyle\sum_{k\neq n}^{\infty}\frac{\langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} – E_k^{(0)}}|\psi_k^{(0)}\rangle\right)\\
&= \displaystyle\sum_{k\neq n}^{\infty}\frac{|\langle\psi_k^{(0)}|H_1|\psi_n^{(0)}\rangle|^2}{E_n^{(0)} – E_k^{(0)}}\\
&= \frac{|\langle l+1, m|H_1|l, m\rangle|^2}{E_{l,m}^{(0)} – E_{l+1,m}^{(0)}}\\
& \ +\frac{|\langle l-1, m|H_1|l, m\rangle|^2}{E_{l,m}^{(0)} – E_{l-1,m}^{(0)}}
\end{align*}
\(E_{lm}^{(0)} = \frac{l(l + 1)\hbar ^2}{2I}\)であるから
\begin{align*}
E_{lm}^{(2)} &= \frac{(p\varepsilon)^2|\langle l+1, m|cos\theta|l, m\rangle|^2}{\frac{l(l + 1)\hbar ^2}{2I} – \frac{(l + 1)(l + 2)\hbar ^2}{2I}}\\
& \ + \frac{(p\varepsilon)^2|\langle l-1, m|cos\theta|l, m\rangle|^2}{\frac{l(l + 1)\hbar ^2}{2I} – \frac{l(l – 1)\hbar ^2}{2I}}\\
\end{align*}
あとは、与えられた結果(問題文最後の式)を代入すればよい。

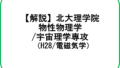
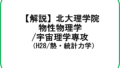
コメント